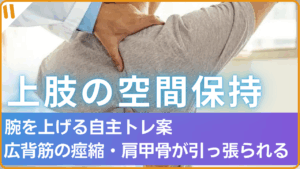【脳卒中という病気と後遺症の片麻痺を徹底的に理解する①】プロローグ・ 脳卒中とはどういう病気か・リハビリに対する誤解
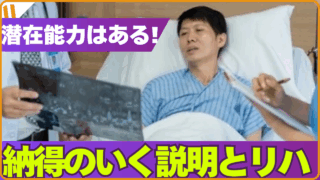
今回の動画では、脳卒中とは一体どんな病気なのかを改めて考えていきたいと思います。
潜在能力が残っている脳卒中片麻痺の方は多いはずですので、改善の可能性を見出していこうという試みです。
目次
リハビリの基礎的な立ち位置
①急性期:出来るだけ残存障害を少なくする
②回復期:障害によってやりづらくなった「動作」を代償手段でやりやすくする
これが前提事項です。
脳卒中が起こるとどうなる
脳卒中の初期症状には様々なものがありますが、一般的には下記があげられます。
・顔の片側がマヒしたり大きくゆがむ
・脚に力が入らず立てない、歩けない
・言葉が出にくい、話しにくい
・目が急に見えづらくなる
・激しい頭痛が突然生じる
病院での処置
脳卒中を起こしたとき、病院ではまずCTやMRIなどの検査でどんなタイプの脳卒中かを調べます。もし脳梗塞なら、血のかたまり(血栓 けっせん)を溶かす薬(t-PA)の点滴やカテーテルを使った治療が行われます。脳出血なら、血圧を下げる治療や、必要に応じて血のかたまり(血腫 けっしゅ)を取り除いたりします。
脳の腫れを抑えるため、頭蓋骨を外す手術が行われるケースもあります。
これらの治療は、発症からの時間が短いほど効果が高いため、すぐに救急車を呼ぶことがとても大切です。
脳細胞へのダメージ
脳卒中により脳細胞がダメージを受けると、死滅した細胞は元に戻ることはありません。
脳卒中により残る後遺障害の程度は様々です。
脳の損傷部位の反対側の手足に運動機能の低下や麻痺が現れることが多く、右脳が損傷されると左側の身体が、左脳が損傷されると右側の身体が動きにくくなります。
後遺症には、運動麻痺や感覚麻痺、言語障害(失語症や構音障害)、視覚障害、高次脳機能障害(記憶・判断力・感情など)、嚥下障害、排尿障害、めまい、痙縮などがあります。これらの後遺症は、脳のどの部位が損傷したかによって現れる症状が異なります。
急性期と回復期を含めての約6ヶ月間に、片麻痺などの残存障害が残った場合、以前のように元通りにはいかなくても、少しずつ身体が動けるようしていくのがリハビリの一つの役目です。
急性期のリハビリ
緊急性の高い、初期治療に関してはドクターが対応する領域です。
一方で、寝たきりによる筋力低下や関節の硬直化を防ぎ、全身のむくみを予防して血圧調整をするといった事は急性期におけるリハビリの大事な役割です。
脳梗塞の時など、命の危険性がなく、ある程度落ち着いた状態だと判断できれば、残存障害を最小限に留めるために、早期のリハ介入や離床は必要不可欠です。
ただ、この時点でのリハビリは、ご本人にとっては、「まだ病室でぼーっとしてるのにリハで強引な事をされた」という記憶として残っているのかもしれません。
これについて、SNSで発信されるような極端な情報に振り回される方も多いです。
急性期で脳が目覚めておらず、十分に体力が回復していないうちから、積極的なリハビリを実施するのは禁忌だとする発信が散見されますが、それは大きな誤解だと個人的に捉えています。
目的はあくまでも残存障害を少なくすること。
急性期での状況を適切に判断しながら、個々の方に応じた最適なタイミングで、立ち座り練習などを実施する意義はあると理解しています。
回復期での下肢装具
回復期における下肢装具の使用に関しても同様で、異なる主張が見受けられます。
回復期でのリハビリは、障害によってやりづらくなった「動作」を代償手段でやりやすくすることが目的です。
なるべく早期に日常生活に戻れるようにするのが目標となります。
意識レベルが乏しい状態で、まだ身体が落ち着いていない時期に、下肢装具を用いてどんどん歩かせてしまって良いのかという疑問を持たれている方もいるようです。
(この是非は状況によります)
下肢装具のひとつの考え方として、早いうちに代償手段を使ってでも歩けるようになった方が良いという思想に基づいており、将来的に不要になったら外そうという設計のもとに運用されています。
反対に、いつまでも経っても下肢装具のままで、日常生活が煩わしい状態になるというのも問題です。本来なら杖も装具も必要ないはずの能力が残っているのに…
下肢装具を使う・使わない・どういう時に使うのか・いつ外すのか・その患者に合ったものなのか…これも議論は尽きません。
リハドクターも含め、患者さんの状態を正しく評価するスキルが問われます。
脳卒中治療の進歩と患者の不満
脳卒中は1951年から約30年間、死亡原因のトップに位置していました。しかし、急性期治療の進歩により、現在ではがんや心疾患に次いで第3位となっています。
医療の進歩により死に至るケースが減ったものの、脳卒中は半身麻痺や言語障害などの後遺症が残る病気であることには変わりありません。
本来であれば医師から丁寧が説明を受けたり、入院中から効果的なリハビリを受けられる環境にあるのが望ましいのですが、現実ではなかなか難しい事の方が多いようです。
こうした患者さんが抱える不満に対しては、リハドクター含め、リハビリテーション専門職の私たちが反省し、改善すべきテーマだと真摯に受け止めています。
まとめ
リハビリは「治す医療」ではなく、「回復を助ける医療」です。
脳卒中による障害は完全には治らないこともありますが、潜在能力は確実に存在すると信じています。
次回からは、脳の仕組みを理解しながら、どういった方法で練習すれば、脳卒中による後遺症に対し、改善の可能性が高まるかを探っていこうと思います。
画内容・チャプター
0:05 脳卒中とはどういう病気か?
0:49 病院のリハは役に立たないのか
2:33 脳卒中片麻痺はどういう状況か
3:04 脳卒中を発症すると
5:07 病院では納得のいく説明がなされない
6:56 脳卒中は1951年頃は死因の第1位だった
8:46 急性期:できるだけ残存障害を少なくする
11:31 リハビリに対する誤解
15:38 リハドクターも理解していない
17:12 回復期:代償手段を使ってでも早期退院を誘導
17:38 潜在能力は確実にある